
神社に参拝に訪れた時によく見かける縦長の旗をのぼりと言います。
とくに稲荷神社でよく見かけるもので、神社の名前や祀られている
神様の名前が記載されているのが一般的です。
「ああ、あれのことか」と思い出す方も多いんじゃないでしょうか?
祈願のぼりはそんな神社のぼりの中でもとくに奉納した人が
自分が祈願した内容を示したものです。
ちなみに神社や祀られている神様の名前が書かれた神社のぼりのことを「奉納のぼり」と言います。
この祈願上りには大きく分けて3つの意味があります。
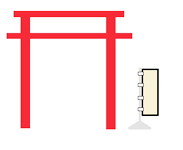
まずは奉納社が祈願した証明として奉納すること。旗の下の部分に
奉納社の名前が書かれていることもあって、「この神社に祈願しました」と証明することができるわけですね。
2つ目は神社を立派に見せるため。参道や鳥居の脇にたくさんの祈願のぼりが立てられていれば
立派な感じがしますし、氏子や参拝者から大事にされているように見えるものです。
祈願のぼりも何もなく、放置されているような神社はちょっと寂しい印象がするものです。
祈願のぼりが立てられている神社はたくさんの参拝者が日頃から訪れており、
氏子たちから愛され、支えられている証拠にもなるわけです。
そして3つ目はその神社のご利益をわかりやすく伝えるためです。
のぼりに記された内容でどんなご利益があるのかすぐにわかるわけです。
神社のイメージカラーであることも
祈願のぼりと言うと白か赤をイメージする方が多いんじゃないでしょうか?
しかし実際にはほかにもいろいろなカラーが使われているのを見ることができます。
赤地に白、白地に赤の祈願のぼりは稲荷神社で一般的なもので、その他の神社では異なるカラーが使われていることもあります。
他には紫や青の生地に白が見られるほか、紺色や緑、白地に色を付けた文字、というパターンも見受けられます。
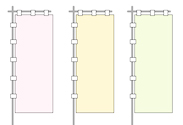
ただやはり圧倒的に「赤と白」の組み合わせが多いのも事実。
その理由としてはそもそもお稲荷さまが日本でもっとも数が多い神社であること、
そして日本の信仰の世界において赤が特別な価値を持っていることが挙げられるでしょう。
還暦のときの赤いちゃんちゃんこなど、ほかにも魔除けのために赤が使われるように、
赤という色そのものが災いが厄を追い払ってくれる力を持っていると昔から考えられているんです。
ですから祈願のぼりに赤を使うのとは「縁起が良い」ということなのでしょう。
願い事を叶えてもらうためにはまず不運や厄を追い払っておく必要がありますから、
縁起のいい色を使うという発想なのかもしれません。
基本的には各神社ごとにのぼりのフォーマットが決まっており、そのなかで
自分が祈願した内容を記したものを奉納することで祈願をした証明とする形となっています。
安く 用途 文字 価格 のぼり旗の役割は 限定感 スマートな対応 お祭り 特徴 データ 使い勝手 活用 設置 注文時 大きさ のぼり旗印刷業者 のぼり旗インクジェット のぼり旗はデメリット 大きさも大小様々なサイズ のぼり旗ネット レストランの案内 感染対策グッズ サンプル画像の活用 制作時の注意点 インパクトのあるメッセージ 奉納のぼりの意味 高い広告効果を得る 伝えたい内容を厳選する 足場の落下防止に使える素材 熱中症対策の呼びかけに ウィンドウフラッグで集客 置き方の工夫 特設インフォメーションを周知させる 魅力のアピールに最適なシルクスクリーン印刷 サイトマップ
